
FICCで毎年年始に行われる、代表・森啓子による年頭挨拶。
この時間は、変化の激しい時代をどのように捉え、私たち自身がどんな問いを持ってブランドや社会に向き合っていくのかを共有するための、大切な場として位置づけられています。
AIの進化、社会の分断、制度や倫理の揺らぎ、そして「豊かさ」や「平和」の意味が問い直される今。私たちを取り巻く環境は、目まぐるしく変化し続けています。こうした時代において、単に起きている事実を追うだけではなく、それらをどのように見つめ、どのように意味づけていくのか。その姿勢そのものが、企業やブランドの在り方を大きく左右するようになっています。
2026年の年頭挨拶で森が掲げたテーマは、「問いを意義に変え、問いを社会の意味へとひらく」。正解を示すのではなく、問いを共有し続けることを通じて、リベラルアーツの哲学を土台に世界を捉え直し、ブランドが社会とどのような関係を築いていくのかを考える時間となりました。本レポートでは、そのスピーチをもとに、2025年という一年を振り返りながら、私たちが何を問い直されていたのかを辿り、2026年に向けてブランドや企業がどのような姿勢で社会と向き合うべきかを探っていきます。
目次
- 意味が見失われていく時代に、何が起きているのか
- AIとDE&Iが提示した「倫理」と「判断」
- 経済と安全保障が示した「豊かさ」と「平和」の再定義
- 環境・生物多様性 ─ 複雑な世界を引き受けるという選択
- FICCが果たすべき役割。問いを手放さない
意味が見失われていく時代に、何が起きているのか
2025年を象徴する言葉たち

2025年という一年を振り返るにあたって、まずはこの数年がどのような文脈の中にあったのかを、時代を象徴する言葉とともに整理してみたいと思います。
2023年は「生成AI元年」と呼ばれ、AIが一気に社会へ浸透した年でした。この年を象徴する言葉として語られたのが “Authentic”(真の、本物の、正真正銘の)です。AIが大量の情報や表現を生み出せるようになったことで、「何が本物なのか」「何を信じればいいのか」という問いが、社会全体に突きつけられました。
その流れを受け、2024年を代表する言葉として選ばれたのが “Polarization”(分極化)です。アメリカ大統領選挙期間を中心に、AIが生成した偽コンテンツや誤情報が溢れ、何が本物なのかについて社会的な合意を得ることが、ますます難しくなっていきました。その結果、対話や理解が深まる一方で、価値観や立場だけが鋭く分かれていく状況も生まれていきました。“Authentic” と “Polarization” は切り離された概念ではなく、生成AI以降の社会が直面してきた、連続した問いとして読み取ることができます。
こうした流れの中で迎えた2025年。この年を象徴する言葉として挙げられたのが、 “Vibe coding”、“Parasocial”、“Rage bait”、“AI slop” といった言葉でした。自然言語でAIに指示を出し、感覚的に開発が進んでいく “Vibe coding”。有名人やインフルエンサー、AIに対して一方的なつながりを感じる一方で、実際には距離がある関係性を示す “Parasocial”。SNS上で怒りや不快感を煽り、拡散を目的とする “Rage bait”。そして、生成AIによって量産される、意味を伴わない低品質なコンテンツを指す “AI slop”。
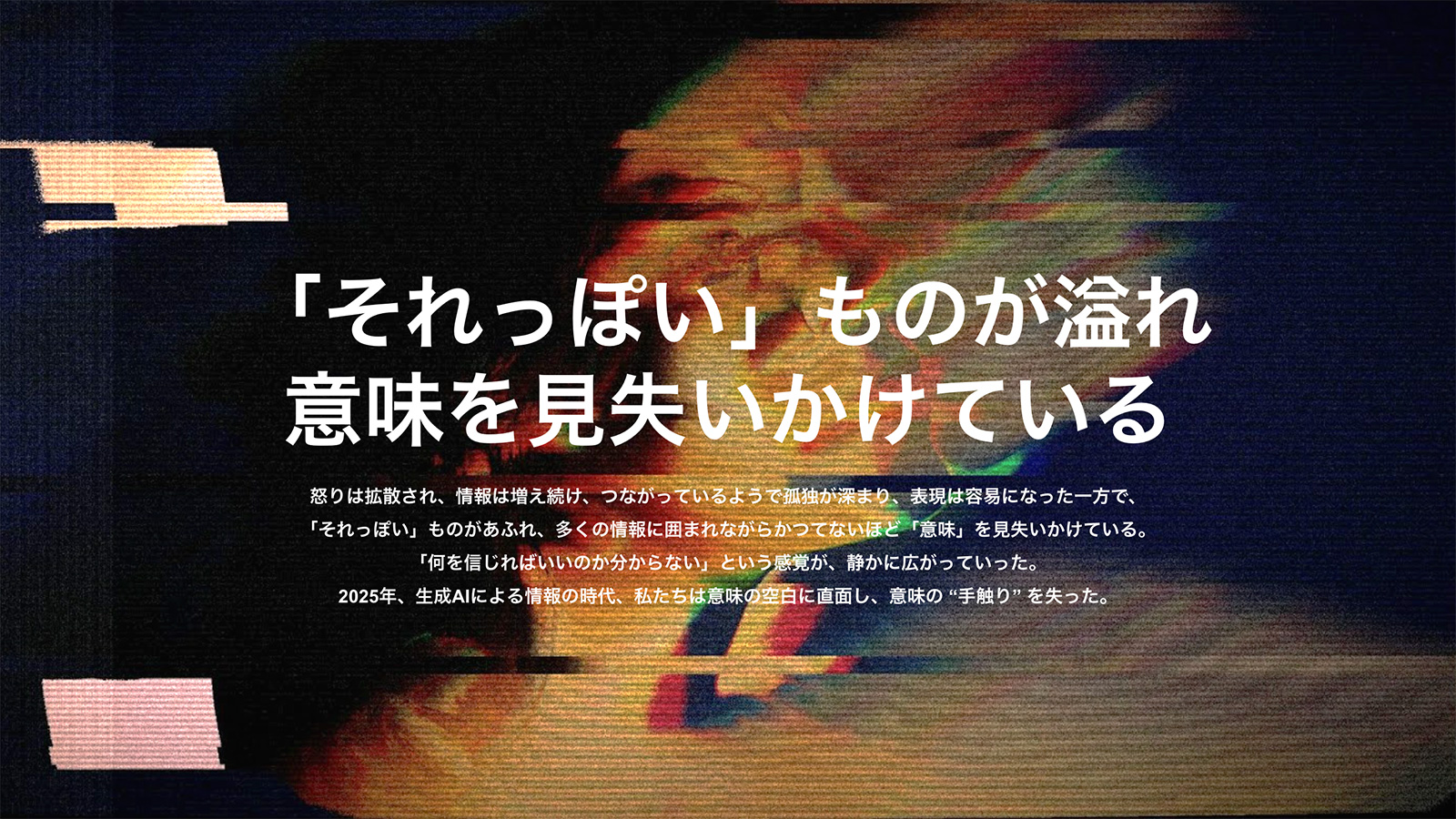
これらの言葉に共通しているのは、「それっぽい」ものが溢れ、情報量は増えているにもかかわらず、そこに確かな手触りや意味を感じにくくなっているという感覚です。情報は溢れ、感情は加速し、つながっているようで孤独が深まっていく。「何を信じればいいのか分からない」という感覚が、静かに社会全体へ広がっていった一年だったのではないでしょうか。
2025年、生成AIによる情報の時代において、私たちは「意味の空白」に直面し、意味の“手触り”を失っていった年でした。
「正解」が消え、「前提」が揺らいだ年

さらにこの年を特徴づけていたのは、危機や変化がもはや象徴的な「ニュース」ではなく、「前提」として私たちの日常に組み込まれていたことです。戦争や地政学的緊張、経済の不安定さは、一過性の出来事ではなく、常に背景として存在し続けていました。
世界は「分断と連帯」のあいだで揺れ動き、「制度と倫理」が交差し、「不確実性」「価値判断」「制度と倫理の共存」という新しい文脈の中で動いていた。そこでは、問題を「解決」すること以上に、どの「選択」を引き受けるのかが、個人にも社会にも静かに、しかし確実に突きつけられていたように思います。
こうした状況のもとで、世界は「正解を探す」ことから、「意味を問う」ことへと重心を移していきました。未来が予測できないからこそ、何を信じ、何を大切にするのか。その「意味づけ」そのものが、私たち一人ひとりに問い返されるようになった年だったのではないでしょうか。
AIとDE&Iが提示した「倫理」と「判断」
AIの進化が浮かび上がらせた問い

2025年、私たちはもう一つの重要な事実と向き合うことになりました。それは、AIの進化そのものが、社会に「問い」を投げかける存在になっていたということです。
生成AIは、私たちの代わりに文章を書き、画像を描き、要約し、判断を下す存在へと急速に広がっていきました。その振る舞いは驚くほど流暢で正確であり、時に人間以上に “それらしく”見える場面も増えていきました。しかし、AIは情報を処理することはできても、何を重視し、何を切り捨てるのかという価値判断そのものを引き受ける存在ではありません。どの情報を強調するのか、どの表現を選ぶのか、どの価値観を前提にするのか。そうした判断は、最終的には人間に委ねられています。2025年は、AIが賢くなった年であると同時に、人間が「考えるとは何か」「判断とは何か」を問い返された年でした。
こうした問いは、AIをめぐる各国の規制のあり方にも色濃く表れています。
AIの規制緩和の姿勢を掲げるアメリカにおいても、2025年には「TAKE IT DOWN Act(リベンジポルノ規制)」が成立するなど、特定分野においては明確な規制が始まりました。
EUでは、昨年の年頭スピーチでも触れたEU AI規制法が「約束」から「実践」へと移行し、実際の規制が動き始めた重要な年となりました。AIの社会的影響を、人権や透明性、民主的価値の維持という価値観の体系として捉え、それを法制度として実装しようとする姿勢が、より明確になっています。
そして日本では、2025年に「AI推進法」が施行され、技術の振興と倫理的安全性の両立を掲げつつ、民間企業に対しては直接的な罰則を設けず、努力義務を中心とした枠組みにとどまっています。

2025年に開催されたAIアクションサミットでは、日本やEU、中国を含む60を超える国と地域が共同声明に署名し、信頼できるAIを国際的に進めていく方向性が示されました。一方で、規制緩和による発展を優先するアメリカとイギリスは署名を見送っています。ここに表れているのは、制度の違いというよりも、「何を守ろうとしているのか」という価値観の差です。
だからこそ重要なのは、制度先行になるのではなく、その背景にある倫理観や姿勢を、人間としてどう引き受けるのかという点です。そして企業やブランドとして、なぜそれを行うのかを明確にし、ブランドアクションとして実装していくことが、いま強く求められています。
理念としてのDE&Iと、現実としての社会

同じ構造は、DE&Iをめぐる議論にもはっきりと現れています。
近年のアメリカでは、DE&Iという言葉そのものが政治的緊張の焦点となり、大学や企業、行政で進められてきたDE&Iに関する活動に対して、政府による大学への多額の資金凍結を通じたコントロールや、企業のサプライチェーンにおけるDE&Iの後退など、反DE&Iの動きが生まれています。ここで起きているのは、単なる多様性への反発ではありません。
実質賃金の停滞、製造業の空洞化、医療や教育費の上昇、地域コミュニティの衰退。こうした変化の中で、不公平感や不安が蓄積されてきた白人労働者層を中心とした人々にとって、DE&Iは「自分たちの困難を無視して、別の誰かを優先する仕組み」と映ってしまった。その怒りは、差別への反発というよりも、見えなくなった安心やマイノリティとなることへの恐怖だったと言えます。
DE&Iは本来、排除されてきた人々の機会を回復する思想でした。しかし制度化される過程で、数値目標や義務化された評価項目へと翻訳され、一部の人々には「自分たちが評価から外される構造」として受け取られていきました。

この文脈の中で、企業やブランドに立ち上がってくる問いは、単に「多様性を推進するか否か」という二択ではありません。異なる立場にある人々が、なぜその価値観に至ったのか。なぜ怒りが生まれ、なぜ恐れが生まれたのか。どのような経験や構造が、その立場を形づくってきたのか。そうした背景を読み解き、可視化し、対話可能な言葉へと丁寧に翻訳していくことが、企業やブランドに求められている役割の一つだと言えるでしょう。
そのうえでブランドは、倫理観とともに、「どの“人々”の安心を、どこまで自分たちとして引き受けるのか」という問いに向き合い続ける存在であることが、あらためて問われています。
経済と安全保障が示した「豊かさ」と「平和」の再定義
経済は数字から、意味へ
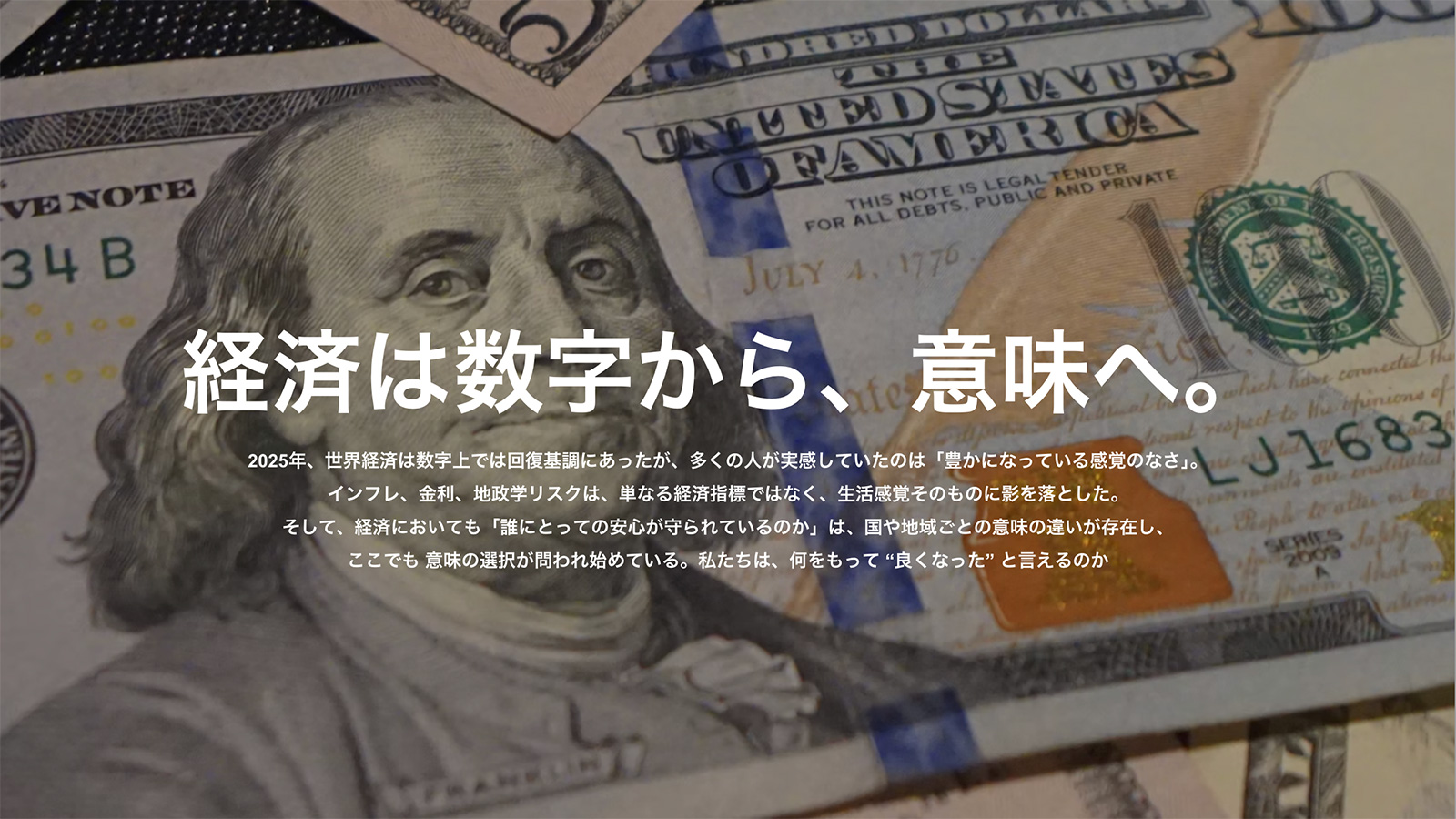
2025年、世界経済は数字の上では回復基調にあると語られていましたが、多くの人が日々の生活の中で感じていたのは、「豊かになっている実感のなさ」でした。インフレや金利、為替、地政学リスクは、もはや単なる経済指標ではなく、住宅ローンや雇用、物価、将来への不安といった形で、生活感覚そのものに影を落としていました。そして経済においても、「誰にとっての安心が守られているのか」は、国や地域ごとに意味の違いが存在し、意味の選択が問われ始めています。私たちは、何をもって “良くなった” と言えるのか。
各国の金融政策は、その変化を象徴しています。
日本では、長く続いたデフレの時代を経て、コロナ禍や世界情勢の影響による物価上昇が生活を直撃しました。2025年末、日銀は政策金利を0.5%から0.75%へと引き上げ、金利は上昇局面に入りました。住宅ローンを抱える世帯や中小企業の資金調達、財政の利払い負担にとって、より厳しい環境へと向かっています。

アメリカでは、2025年に複数回の利下げが行われ、年末時点で政策金利は3.50〜3.75%まで引き下げられました。そこにあったのは、労働者や中間層の家計、企業の資金繰りを守り、社会の分断をこれ以上悪化させないための配分の判断でした。
ヨーロッパでは、成長よりも制度の持続性が優先されました。金利は通貨への信頼や社会モデルの安定を支える装置として扱われ、企業には利益の最大化だけでなく、「制度に参加する主体」としての責任が強く求められるようになっています。
中国では、住宅市場や地方財政の安定を軸に、社会秩序そのものを守るための慎重な緩和が続きました。そこでは、安心は個人の自由よりも、社会全体の安定と結びついています。

こうして見ると、各国の判断の背後には、それぞれ異なる「安心」の定義があることが分かります。そしてその選択は、企業やブランドにも確実に返ってきています。価格は誰の購買力を守るためのものなのか。雇用は誰を守るための設計なのか。サプライヤーを含めた人権や労働、環境を、どこまで責任を引き受けるのか。ブランドとして、どの秩序の上で事業を続けていくのか。経済の問いは、そのまま企業やブランドの価値観の問いへと接続していきます。
成長とは何か。私たちは何を “豊かさ” と呼ぶのか。効率や規模の最大化が、豊かさの唯一の定義だった時代は終わりつつあります。何をもって “良くなった” と言えるのか。誰にとっての安心が守られているのか。この問いは経済の話であると同時に、私たちがどんな暮らしを望み、どんな未来に責任を持とうとしているのかという、価値観そのものの問いでもあります。
安全保障・平和の意味 ー 私たちは何を守るのか
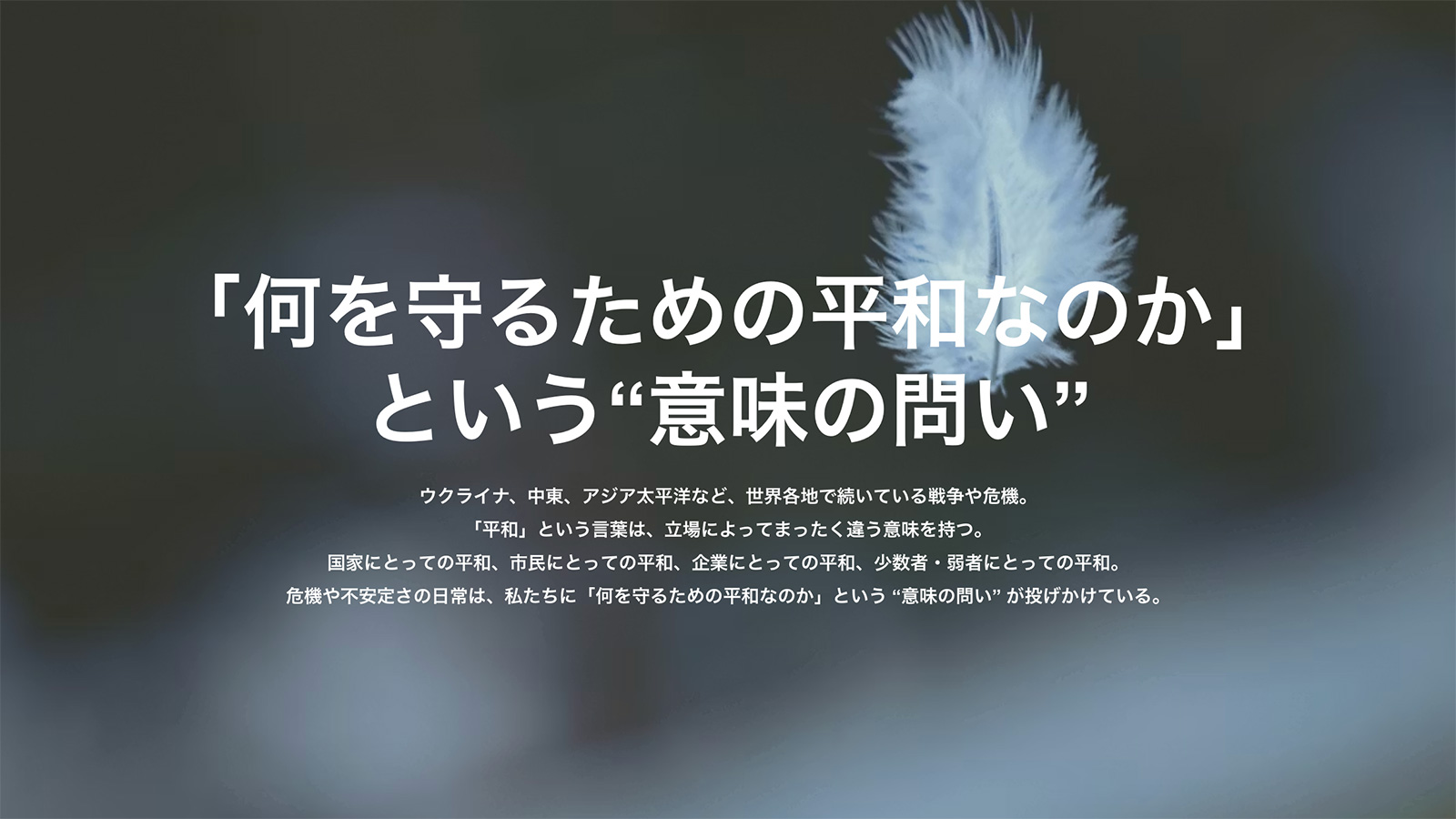
同じ構造は、安全保障の文脈でも現れていました。戦争や緊張は、もはや例外的な出来事ではなく、“日常の背景” として存在し続けるものになっています。「平和」という言葉は、国家、市民、企業、そして少数者や弱者と、立場によってまったく異なる意味を持ちます。危機や不安定さが日常となった世界は、私たちに「何を守るための平和なのか」という意味の問いを投げかけています。
その問いが、最も重く、複雑な形で表れているのが、イスラエルとパレスチナ自治区ガザをめぐる状況です。1948年のイスラエルの建国宣言以降、民族と民族がそれぞれの地を守るために向き合い続けてきた、長い紛争の歴史。その延長線上で起きているイスラエル・ガザ紛争は、歴史的背景から見ても、最も解決が難しいとされています。

この現実の中で、「平和」の意味は大きく分かれています。
イスラエルにとっての平和は、「存続」を守ること。それは、国家として生き残れるかどうかという、存在そのものをめぐる問いであると主張しています。周辺地域からのテロ行為を含む脅威から国を守ることが、自らの存在を守ることと強く結びついています。
一方、パレスチナ自治区ガザにとっての平和は、「尊厳」を守ることです。長い紛争の中で土地を追われ、多くのパレスチナ人が難民となってきました。ガザ紛争では多くの一般市民が命を落とし、日常生活そのものが奪われ続けています。ここで語られる平和は、生き延びること、人間としての尊厳を保つことと深く結びついています。
そして、国際社会にとっての平和は、「秩序」を守ること。国連決議や国際会議、停戦合意といった枠組みは作れるものの、その実行力や正当性は常に不足しています。本来は中立であるべき人道支援さえも、政治的な選択と切り離せない状況にあります。

同じ「平和」という言葉を使いながら、守ろうとしているものが異なるからこそ、合意は常に困難になります。平和はもはや一つの状態ではなく、「何を守るのか」という設計の問題へと変わっています。そして、ここでも問われているのは、どの価値を守るために、どこまで責任を引き受けるのかという判断です。

こうした現実の中で、多くの人が無力感と罪悪感のあいだに立ちすくんでいます。遠くで起きている出来事を知りながら、何もできないという感覚。それでも、何かを引き受けなければならないという圧力。この「社会的苦悩(Social Suffering)」は、国家だけの問題ではなく、私たち一人ひとりの倫理の問題でもあります。

ここで問われているのは、それぞれの立場における平和の意味と、その背後にある歴史や政治的選択を理解しながら、企業やブランド、そして私たち自身が、「誰の苦しみに目を向けるのか」「どこまで責任を引き受けるのか」を考え続けることです。これはもはや国家間の力学や地政学の問題ではなく、「倫理と想像力」の問題です。
平和とは、常に問い続ける意思そのものであり、他者とともに考え、答えのない状況を引き受け続ける姿勢です。企業がこの姿勢を持つとき、ブランドは単なる経済主体を超え、社会の中で「意味を編み続ける存在」になります。それこそが、この時代においてブランドが果たすべき、最も誠実な役割なのではないでしょうか。
倫理と想像力の問題として企業やブランドと向き合う

こうして年始挨拶を行い、それを発信すること自体も、FICCが大切にしているアクションの一つです。向き合う企業やブランドとともに、問いに向き合い、対話を重ねながら、その問いを社会にひらいていくこと。倫理と想像力の問題として、どのような問いを立て、どのように共有していくのか。
IKEAの “One Little Thing” というストーリーに、はじめて触れたのは5年前、2020年のことでした。カナダで始まったLEDライトのプロモーション。それはやがて、オーストラリアやルーマニア、クロアチアへと広がっていきました。映像の中で語られているのは、LEDライトの機能や環境性能ではありません。「一つのささやかなこと」が、もし孤独な一つではなかったとしたら。その小さな一つひとつが重なり合ったとき、想像もできないほど大きな問題を解決する力になるかもしれない、という問いです。
LEDライトという一つの商品を扱ったブランデッドコンテンツでありながら、そこで描かれている世界は、LEDライトの世界を超越しています。小さくてささやかな行動が集まったとき、世界のあり方そのものを変えていく可能性がある。そのメッセージは、環境の話であると同時に、これまで見てきた「平和」にもつながると感じています。
FICCがブランドの力になるとき、大切にしているのは、正解を示すことではありません。問いに向き合い続け、対話を重ねる中で見えてきたブランドアクションとともに、社会に問いを投げかけていくこと。たとえそれが一つの商品であったとしても、その背景にある思想や姿勢が、人々の内側で何かを動かし、社会との関係性をひらいていく可能性はあるはずです。
環境・生物多様性 ─ 複雑な世界を引き受けるという選択
倫理とリーダーシップ、リベラルアーツの視点から

2025年は、環境・生物多様性というテーマが、単なる環境保護の枠を超えて、倫理やガバナンス、社会体制そのものを問い直す問題として立ち上がった年でした。気候変動や生態系の崩壊は、もはや予測や警告の対象ではなく、私たちの日常を規定する前提条件となりつつあります。こうしたパラダイムシフトの中で、既成概念を問い直し、何を前提として世界と向き合うのかを考え直すリベラルアーツの哲学に基づくリーダーシップを感じられる動きが見られました。
この流れを象徴する出来事の一つが、2025年にブラジル・ベレンで開催されたCOP30です。アマゾンという象徴的な場所で開かれたこの会議では、国家間交渉だけでなく、先住民族や市民社会、宗教コミュニティ、科学者、アーティストなど、多様な立場の人々が参加し、それぞれの視点から環境をめぐる問いが交わされていきました。環境問題に対して、政策や技術の話にとどまらず、「なぜ合意された約束が実行されないのか」という根源的な問いに、倫理的側面から向き合いました。

COP30では、先住民族の権利と役割が、これまで以上に明確に位置づけられました。また、森林を「守ること」そのものを経済的価値として成立させる「熱帯林永久基金(TFFF)」や、国家間の進捗評価にとどまらず、市民社会や倫理的視点を組み込む「グローバル倫理ストックテイク(GES)」といった枠組みも提示されました。そこにあったのは、環境を犠牲にしながら成長するという発想から、価値観そのものを組み替えていこうとするパラダイムシフトでした。
その中でブラジルは、16世紀フランスの作家ラブレーの言葉「良心なき科学は魂の破滅を招く」を引用し、サステナビリティとはデータによる実証だけではなく、倫理的な意識に根ざしたものでなければならないと訴えました。愛、連帯、コミットメント、責任。これまで交渉のプロセスから抜け落ちがちだった、そうした倫理的側面を統合していくこと。その姿勢とリーダーシップが、いま強く求められているのです。

「生き残り続けるもの、淘汰され散っていくものも、それらすべてが美しいと私は信じたい。」
これは、チャールズ・ダーウィンが残した言葉です。
FICCが20周年を迎えた際にも、この言葉を紹介しました。ダーウィンの進化論を、企業やブランドの生存競争や勝ち残りの理論として語るのではなく、ダーウィンという一人の人間が抱いていた想いや美学から見つめていくことの大切さ。
ダーウィンが残したこの言葉、その根底にある美学が示しているのは、これからのリーダーシップに求められる視点でもあります。それは、「人の想い」からサイエンスの世界を見つめ直すという、“Arts & Scinece” の本質、美意識と倫理観です。複雑で答えの出ない課題に対しても、この姿勢をもって向き合うことで、既成概念を問い直しながら、未来につながる新たな問いをひらいていく。その態度そのものが、リベラルアーツの哲学であると信じています。
FICCが果たすべき役割。問いを手放さない

ブランドとは、売るため、認知を広げるためのものではありません。世界の中で「どのように生きるか」という姿勢そのものを体現すること。そして、社会の中でどの価値を支持し、どの現実に目を向けるのかを選び取ること。それは同時に、倫理的な判断であり、文化的な判断でもあります。だからこそ、異なる価値観が出会い、考え、対話できる “場” をつくること。その積み重ねが、ブランドの輪郭を形づくっていきます。
いま、ブランドは「語る存在」から「共鳴する存在」へと変わりつつあります。一方的に語るのではなく、共鳴が生まれる場をつくること。共鳴とは説得ではなく、相手の内側で何かが動くことです。「答え」を示すのではなく、「問い」を差し出すこと。「正解を示す」のではなく、問いを共有すること。問いを人々の内側に灯すこと。ブランドに求められているのは、強い主張ではなく、「誠実さ」や「共鳴力」です。

FICCは「ブランドとは何か」を語る会社から、「ブランドを通じて、社会とどう関わるか」を創造する会社へと進化していきます。その土台にあるのが、リベラルアーツの哲学です。リベラルアーツとは、正解を与えるための知識ではなく、世界を理解し、意味づけるための力であり、人やブランドに問いを与えるものです。そしてブランドマーケティングとは、その問いを社会との関係性の中で育て、社会の意味へとひらいていく営みです。
一つの答えや正解だけがある世界ではなく、また、自分のことや今のことだけが良ければいいという世界でもなく、互いの存在を豊かなものとして、社会や未来に対して貢献するリーダーシップを発揮していくこと。古代ギリシャ・ローマにおいて、リベラルアーツの起源がそうであったように、それは、個人の内面を磨くものではなく、公共的存在として、公共に参与する人として、囚われることなく自由に生きていくこと。
「何を問うのか」という根源的な問いは、AIではなく、人間にしか決めることはできません。だからこそ、これからのクリエイティブに求められるのは、「問いの深さ」であり、「世界を感じ取る感性によって、問いを社会の意味へとひらいていく力」です。リベラルアーツの哲学を大切にするFICCだからこそ、その力になることができると信じています。
世界中で翻訳された『Einstein’s Dreams(アインシュタインの夢)※』が描いた世界のように、そしてダーウィンが残した言葉のように、人と自然科学が融合する “Arts & Science”。そこには、リベラルアーツの世界があります。理性と感性を分けない。科学と詩を分断しない。経済と倫理を切り離さない。“Arts & Science”の往復こそが、これからの時代の想像と創造を支えていくと考えています。
正解のない時代において、最も誠実な態度は、「問いを手放さない」こと。
そして、「問いを意義に変え、問いを社会の意味へとひらく」こと。
何を大切にし、何を信じ、どんな未来を選び取るのか。
「どの立場に立つか」ではなく、「どの声を聴くことができているのか」を問い続けていくこと。
異なる価値が出会い、対話が生まれる場をつくること。
それが、この不確かな時代において、私たちFICCが果たすべき役割です。
FICCは、企業と社会のあいだに立ち、問いを紡ぎ、意味を翻訳し、未来へと手渡していく存在でありたいと考えています。
LIBERAL ARTS empowers BRAND MARKETING
ー 問いを意義に変え、問いを社会の意味へとひらく
※ Einstein’s Dreams(邦題:『アインシュタインの夢』)
アルバート・アインシュタインが相対性理論を研究していた時代の「夢」をモチーフに、時間や存在を詩的に描いた小説。著者はMIT教授のアラン・ライトマン。科学と人文学が交差する物語を通じて、理性と感性、科学と詩を分けずに世界を捉える “Arts & Science” =リベラルアーツの思想を体現した作品として知られている。